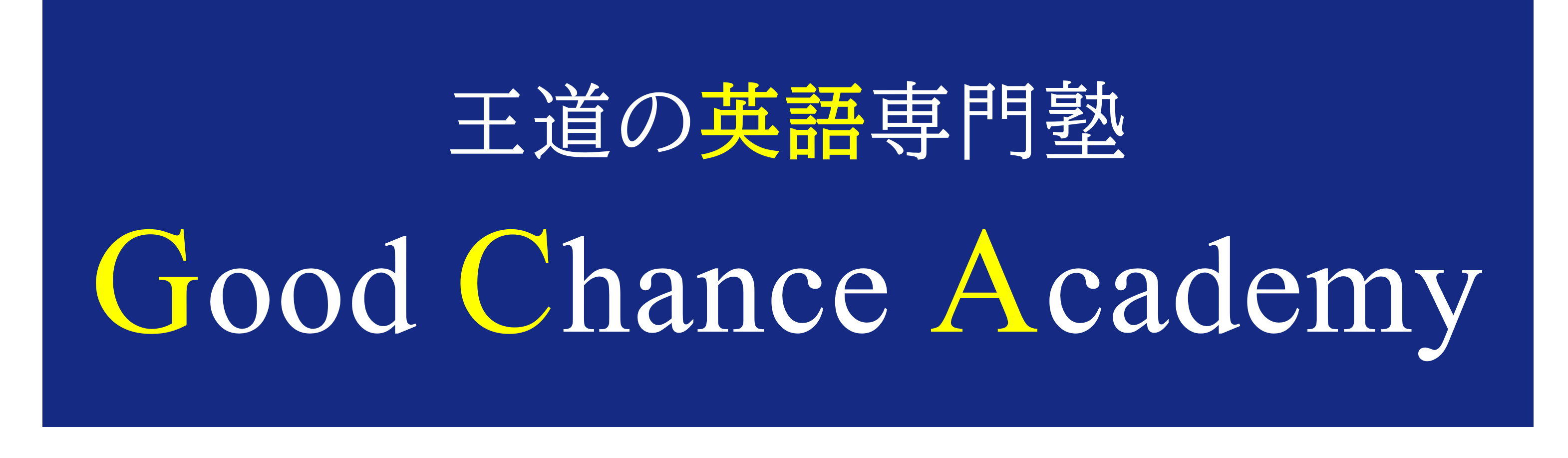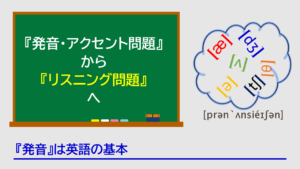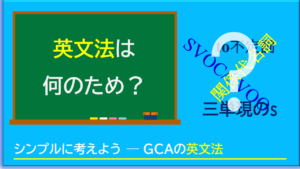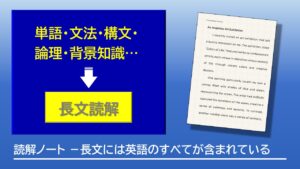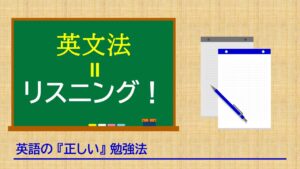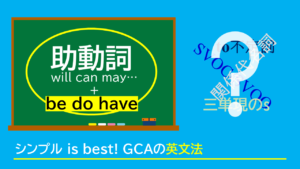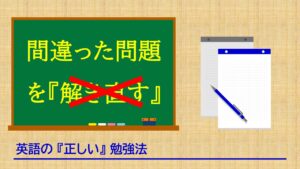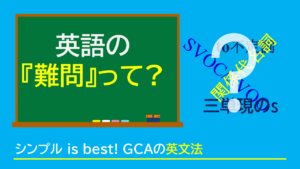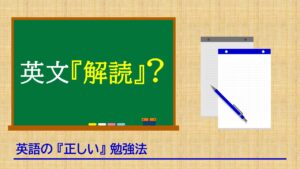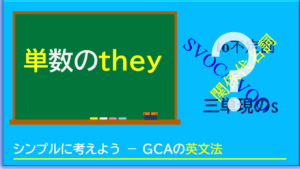福岡市天神の英語専門塾GCA・代表のグッチャンです。
共通テストでは「発音・アクセント」と「文法・語法」問題、つまり(旧)センター試験の第1問・第2問がなくなりましたね。
『文法』は時代遅れか??
そのためか、
「文法を教えるのはもう時代遅れだ。共通テストに対応できるように、今後は長文読解・リスニングを中心に指導するべきではないか」
「いや、文法問題がなくなってしまうと生徒たちの文法への理解が不十分になってしまう。すぐに復活させるべきだ」
といった議論がよく聞かれます。
はたして英文法の学習はもはや時代遅れになってしまったのでしょうか?
『文法=文法問題』ではない
確かに『なんとなく』意味がつかめる場合がある長文問題と異なり、『文法問題』があることで中高生の文法への理解が深まっていたことは事実です。
文法の問題演習やテストを行なう意義を完全に否定するわけではありません。
ところが同時に、いわゆる『重箱の隅』問題と呼ばれるマニアックな文法問題が異常に発達し、『文法イコール文法問題の解法テクニック』という風潮が広まってしまったことも忘れてはいけません。
これは日本の英語教育に本当に大きな傷跡を残しました。
つまり、四択・穴埋め・並べ替え問題を数学の難問に取り組むようにじっくり考えて『解く』のが文法の学習だと、大半の英語指導者・中高生が思い込んでしまったのです。
その結果、文法問題を解くことにしか使えない文法知識が蔓延してしまいました。それが皆さんもうおなじみの「中高6年間も勉強しているのに英語が使えない」という決まり文句につながるのです。
(ただ、入試というのは選抜試験であり、誰もが正解できる基礎的な問題を出題することはできません。だからこのような現状になったのも仕方ないことではあります)
迷走が続く英語試験改革ですが、少なくとも『文法問題を解くためだけの文法』という風潮を打ち破るという点においては絶対に前に進めなければいけません。『伝説の難問』など英語学習に百害あって一利なしです。
文法は『4技能』の基礎
一方、時代遅れの『文法』に対して、新しい『4技能』時代の到来、という意見が少なくありませんが、これもまったくの見当違いです。
本来の文法は英語学習の基礎中の基礎であり、必要不可欠なものです。
たとえば、4技能のうちのひとつ『読む(reading)』について。
以下はある物語文の抜粋ですが、きちんと意味をとることはできますか?
“…earthquakes do happen sometimes even in Britain. Don’t they, Daddy?”
“We would have felt it,” my father said.
……
……
はい、答えです:
「イギリスでだってときどき地震くらいあるよね、お父さん」
「うーん、(あるんだったら揺れるのを)感じたことがあるはずだろうね…」と父は言った。
……
この何気ない親子の会話ですら、高校生がいちばん苦労する仮定法過去完了(would+have+過去分詞形)がきちんとわかっていないと正確に理解できないのです(引用は会話文でもあるため、『4技能』の『話す(speaking』についても同じことが言えます)。
つまり文中の「お父さん」は「イギリスに地震はない」と娘に対して遠回しに反論しているわけです。
……
文法知識を試すのに、難解さを求めるあまり暴走しがちな、旧来の四択・穴埋め・並べ替え形式の『文法問題』は不要です。
長文の中に穴埋めや並べ替えを忍び込ませる必要もありません。
“なんとなく”正解できるゆるい長文問題ではなく、一語一語正確に読み取っていないと正解が選べないような、クオリティの高い読解問題が求められているのです。