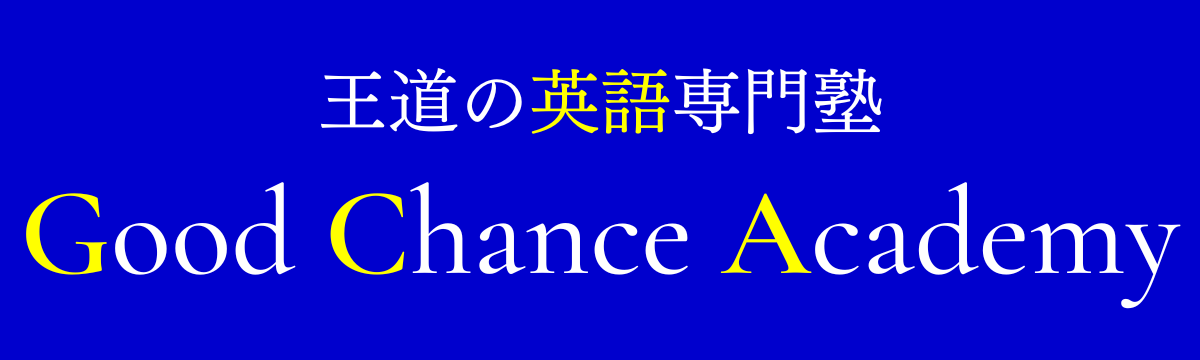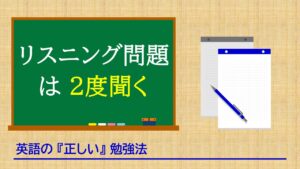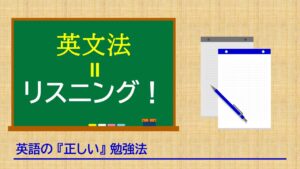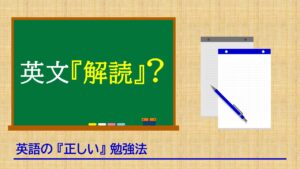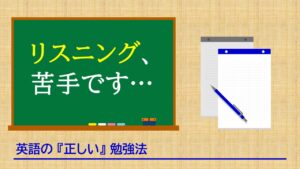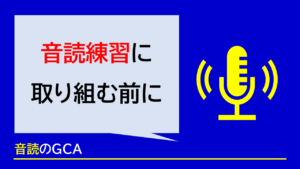福岡市天神の英語専門塾GCA・代表のグッチャンです。中1生は音声中心の学習を早めに始めましょう。
文法ドリルの罠
中1ではまず英語の発音とフォニックス(発音・つづりの関係)を優先的に学習すべきだと書きました。今回はもうひとつのポイントについて。
それは、脊髄反射的な語順の感覚 です。
ワークや問題集では、選択問題・穴埋め問題・書き換え問題・並べ替え問題の順序で新しい文法事項を練習します。確かにこのような練習で頭を使うことにより語順の感覚を身につけることもできます。ゲーム的な楽しさもあるでしょう。
ですが、英語を実際に使う場面では、単語を選択肢から選ぶことも、与えられた単語を並べ替えることも、虫食い文の穴埋めをすることもありません。
英語を「使う」ということは、センテンス(文)を丸ごと聞き・読み・書き・話すことなのです。英語の語順でパッと理解できる、発信できる感覚が身についていないと、センテンスをスムーズに作ることはできません。
そのためには、やはり聞く・音読する練習が非常に重要です。なぜかというと、書かれた英語は後ろからでも読めるからです。
文字だけで練習しているといつまで経っても「英語の語順は日本語の逆だ、だったら後ろから読めばいい」という感覚から抜け出せません。たとえるなら現代の中国語を勉強するために、漢文の返り点の打ち方を練習するようなものです。
一方、音声は聞くときも音読するときも一瞬で消えてしまうため、否応なしに英語の語順に慣れざるを得ません。
「短文暗唱」を中心に
ですから、文字だけで練習するワークや問題集は、練習の手段というよりも、練習が身についているのか、身についていないならばどこを練習すべきなのかをあぶり出すチェックの手段という位置づけにすべきです。
英語の語順は見事に日本語と逆なので、中1生に音読や短文暗唱の課題を出すと大半が非常に苦労します。正直、そこで英語が嫌になってしまう生徒もいます。
しかし、そこが最初の通過点です。そこをクリアできないことには英語は伸びません。少なくとも4技能型のテストや、実際の使用に耐えうる英語力はつきません。難しい試験問題ならじっくり考えて解けるのに、その問題に使われているものよりはるかに簡単なセンテンスを丸ごと作れない(つまり使えない)状態に陥ってしまいます。
ぜひ中1のうちに、
① 文法ドリルの英文はすべて暗唱、脊髄反射的な英語の語順を身に付ける
② その成果をワーク・問題集でチェックする
という学習習慣を必ず身につけてください。暗唱練習を飛ばして問題演習だけを繰り返しているケースがあまりに多すぎます。