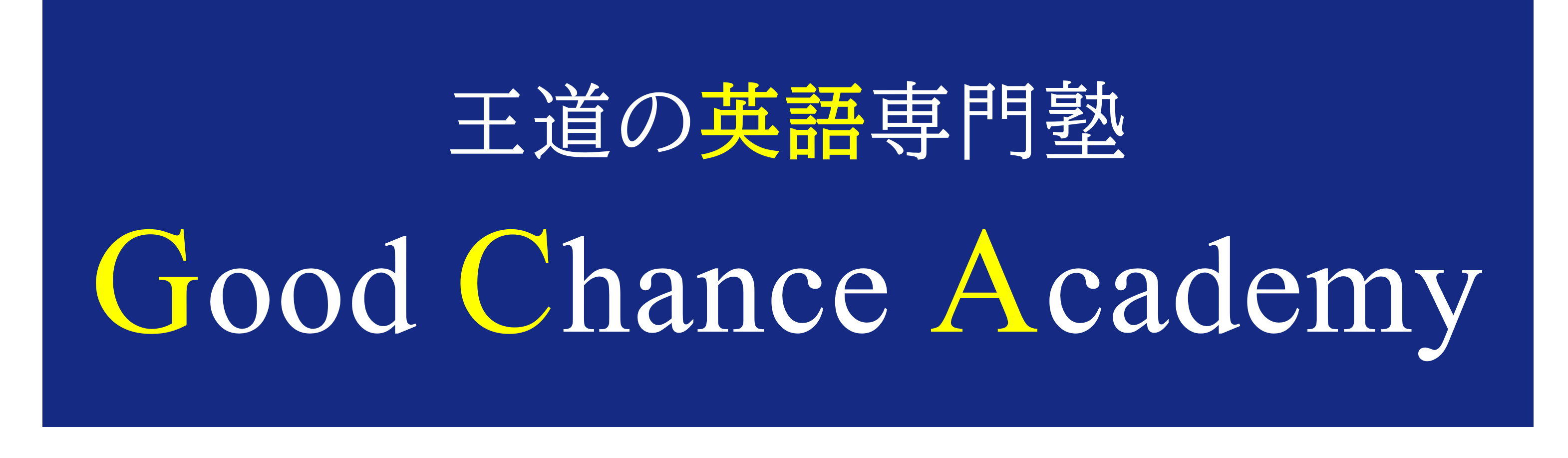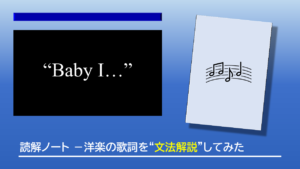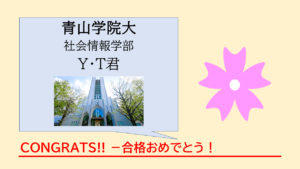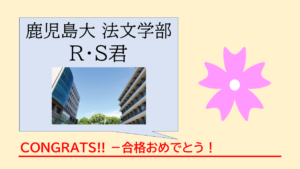福岡市天神の英語専門塾GCA・代表のグッチャンです。ついに2020年に大学入試センター試験が廃止されますね。
これからの高校生に求められる学力
センター試験だけでなく入試のシステム全体が,受動的に暗記した知識量だけが問われるものから,能動的に問題を発見したり周囲と協力して新たな価値を創造していく能力が問われるものへと変化していくと言われています。
2016年に文科省の「高大接続システム会議」が発表した最終報告では,高校生が身につけるべき能力として,
①十分な知識・技能
②それらを基礎にして答えがひとつに定まらない問題に自ら解を見出していく思考力・判断力・表現力等の能力
③これらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
の3つが挙げられています。
ここでは,どうしても目新しい②や③ばかりが注目を集めてしまいます。ですが,やはり学力の中心は①の「十分な知識・技能」であることには変わりはありません。
インプットを軽視しない
もちろん,『重箱の隅をつつくような』と形容されてきた一部の入試問題を擁護するわけではありません。
だからといって,今後は思考力・判断力・表現力が重要なので,知識や技能をインプットする練習をおろそかにしていいと考えるのはあまりに短絡的です。
問題にされるべきは,思考力・表現力 ⇔ 知識・技能 という対立軸ではないのです。
重要なのは,思考力や判断力・表現力に即座に結びつくように,知識や技能のインプットができているかということです。
(続きます)