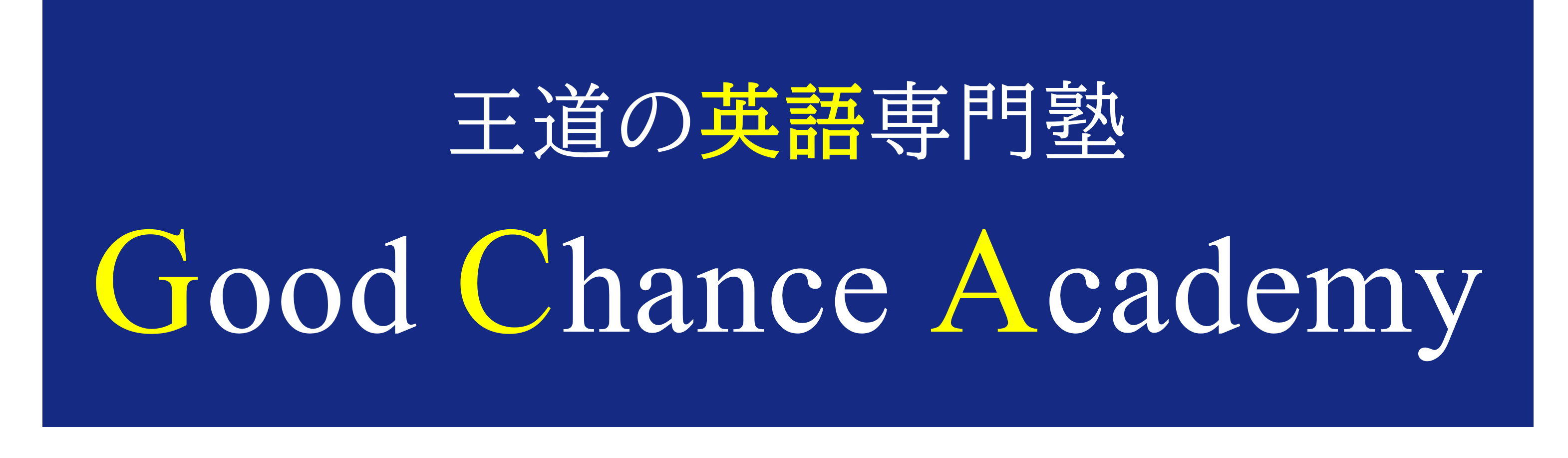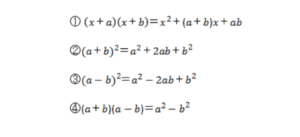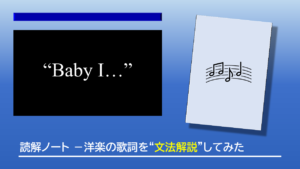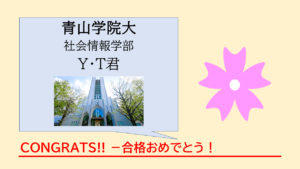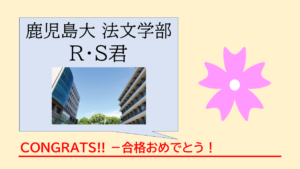福岡市天神の英語専門塾GCA・代表のグッチャンです。文法をきちんと理解するコツについて。
基本の形に戻してみる
難しい文法というのは,たいてい述語動詞(V)の部分がこみいっているものです。
例えば,
He might have done well on the test.
(彼はテストの出来がひょっとするとよかったのかもしれない)
という文があります。
might have done のあたりが難しいですね。
こういうときは丸暗記に頼らずに,もともとどんなセンテンスが変形してこの形になったのか,いったん基本に立ち返ってみましょう。
……
He might have done well on the test.
…まず助動詞 might を現在形に戻します
He may have done well on the test.
(彼はテストの出来がよかったのかもしれない)
…さらに現在完了形を作る have をはずすと
He may do well on the test.
(彼はテストの出来がいいかもしれない)
…最後に助動詞 may を外すと
He does well on the test.
(彼はテストの出来がよい)
最後は中1生でも理解できる文に戻りました。
1ステップずつ比較する
ここからもう一度逆にたどって,助動詞などを加える前と後をつねに比較しながら,その違いを理解していくのです。
一見遠回りに見えますが,現在完了形のニュアンスや助動詞の過去形の意味もわからないまま,いきなり might have done…, must have done…, should have done…, などと丸暗記するよりはるかに文法問題がすっきり理解できますし,何よりもこの文法を実際に使うことができるようになります。
本物の理解は「比較」することから始まるのです。