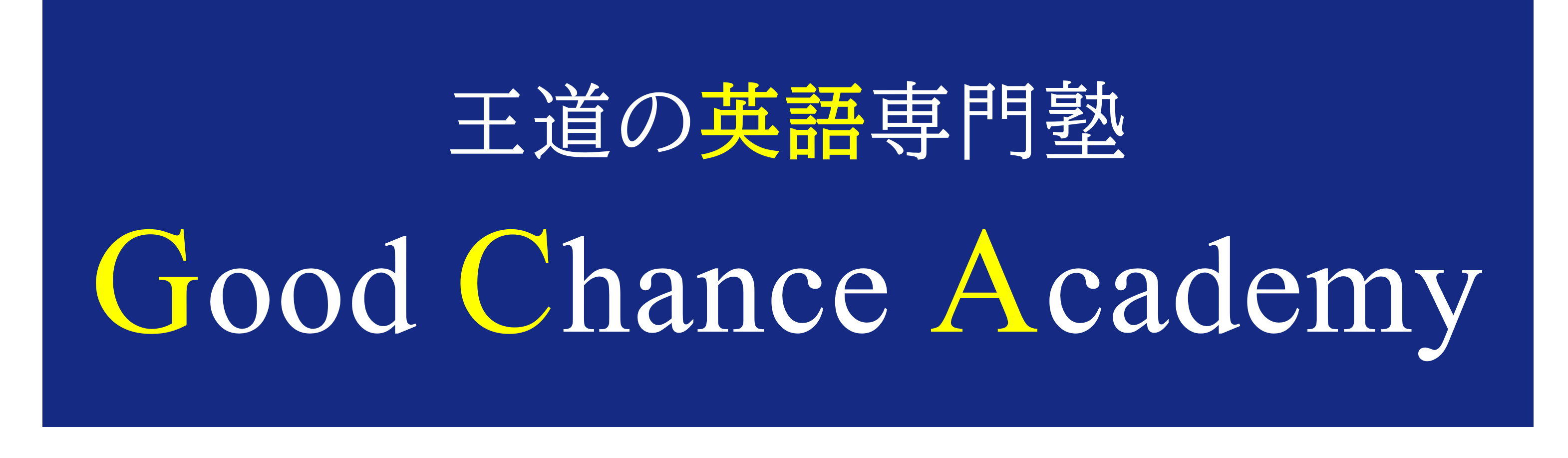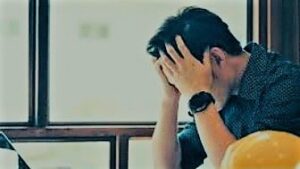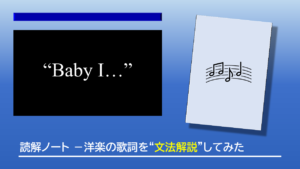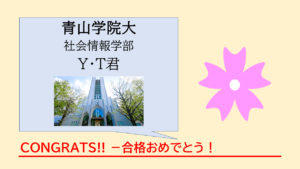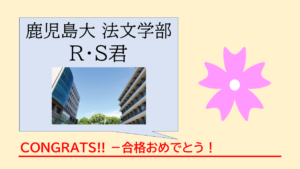福岡市天神の英語専門塾GCA・代表のグッチャンです。「音読」は決して丸暗記のような次元の低い練習ではありません。
「音読」低レベルな練習なのか?
最後に「音読のような単調な練習ではなくて,もっと高度なことを教えてほしい」という意見についてです。
まず前々回で説明したように,音読練習はそれほど単純なものではありません。
例えば学校の運動部では,ミニゲームや練習試合をする前にランニングや筋トレ・1人での基本練習・数名での基本練習と段階的な練習を行なうと思います。
様々な形式の基本練習がほとんどで,ミニゲーム・練習試合や高度な戦術についてのミーティングは,割合としては実はかなり少ないのではないでしょうか。
英語学習における問題演習や講義というのは,スポーツにおける練習試合や戦術の解説と同じです。それだけやっても絶対にうまくはなりません。様々な基礎練習が十分に行われていることが前提なのです。
また,音読というのは練習の「内容」ではなくあくまで「方法」です。文法の例文を「音読」で理解し,長文を「音読」で定着させ,単語を「音読」で身につけ,添削を受けた作文を「音読」して自分のものにするのです。
文法問題の「難問」などでも,講師の解説を受けて「なるほど」と納得するだけでは不十分です。理解は英語学習の準備段階にすぎません。
長文も同じです。映像講義などでキーセンテンスやディスコースマーカー・選択肢の見抜き方についての解説をじっくりと聞き,SVOCMなどと構文をとっただけで学習終わらせてはいけません。
まるでそれはピアノのレッスンで,ひと通り運指を習っただけでもう次の課題曲に移るようなものです。本当の学習はそこからなのです。いったん理解した文章を5回10回と,リピーティング・サイトトランスレーション・バックトランスレーション・オーバーラッピング・シャドウイングと様々な音読練習を行ない,自分のものにしていくのです。
…いかがでしょうか。音読のイメージが少しは変わりましたか。